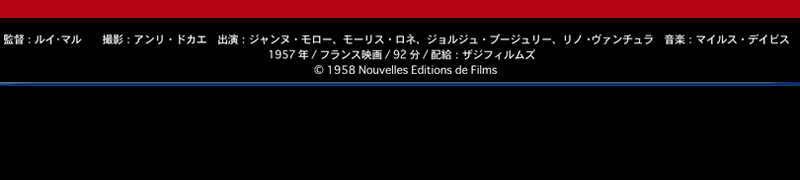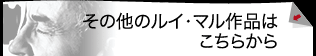色彩に合う音楽というのは、ある。鮮烈な赤のための音色や、眩暈を喚び起こすほど深い、暗い濃茶のための音響や、溢れんばかりの七彩のためにフィールドで採集されたメロディも。映画音楽で肝心なのは、その画像の彩りにその音色が相応しいかどうかを判断できる耳が、制作者——サウンド担当者——に具わっているか、否かだ。その他の判断のポイントはじつは瑣末(取るに足らない、「たかだか」それだけの事柄)でしかない。
無声映画の時代は、関係なかったんだろう。
そして、カラー映画の時代に初めて"有効"となった点だろう。僕には、そうだ。サウンドトラックの、その色彩的感性。
しかし、待て、と思う。無声映画の次がカラー映画の——天然色映画の、総天然色のそれの——時代でいいのか。違うだろ。モノクロームの時代がある。そうだ、白黒映画だ。
そして、『死刑台のエレベーター』が、いかなるサウンドトラックが色彩なき(と即断されている)白黒映画にぴたりと嵌まり、かつ嵌まり続けるのかを示す。そのマイルス・デイビスの音楽。そのマイルス・デイビスが制作を担当した映画音楽。即興セッションだった、という。即興とは、肉体の反応がメンバー間で感染する、その速度の"表現"だ。かつ、最初にその速度が発するためのコンセプトなり、何事かなりが、つねに崩壊をまぬかれ続ける宿命を背負っている"表現"だ。
それをマイルスは理解している。
理解して、画面に寄り添い続けている。
当たり前だが、白黒映画にも実際には色彩がある。秘められるようにして、存在する。存在しないのだったら「モノクロームに色調はない」ことになり、そうだと断じる人間がいるのならば、君には肉体が欠如しているのだと僕は言おう。さて、ルイ・マルだ。ここで監督のルイ・マルに触れる。これはルイの初監督作で、ここでルイは『死刑台のエレベーター』を徹底的に「作り込まれた」作品として仕上げている。
作り込みとは、足し算ではない。
作り込みとは、引き算だ。
削ぎ落とせない人間は、計算も感性も(感性すらも!)なしに、ただ過剰に"表現"を装飾する。
愚かしい。
ルイ・マルはこの『死刑台のエレベーター』で、僕たち/君たちに言うのだ。全てを切り詰めよ、と。豊かさのために——あるいは"豊穣"なる収穫に備えて——切り詰めよ、と。
即興と作り込みが、ゆえにこの瞬間、この作品上で両立する。
普通はしないよ、両立は。それから、他にも理由がある。これは制作当時の都市の映画だし、現在=現代の映画だ。オフィス(の描写、描出)がそれを物語り、また車がそれを物語っている。車とは、エンジンを搭載したあの車だ。速度の"乗り物"だ。ひたすら速度を表わす。アクセルを踏みたい人間に、その"表現"の場を与える。
これは速度の映画だ。
だからサウンドトラックに、即興は適応可能だった。
理解してもらえるだろうか。
そしてこれはジャンヌ・モローの映画だ。
その目ではじまり、その声で終わる。
理解してもらえる。観れば。ジャンヌ・モローが公衆電話にいて、それがオープニングで、他にはオープニングは存在しない。結局、あらゆる『死刑台のエレベーター』内の速度はそこから発している。ジャンヌは、そこに「入って」いるのに。ほとんど不動ですらいるのに。
目だけで語れる女優というのは、いる。たぶん、僕はこれで『死刑台のエレベーター』に関しては充分に語った。あるいは語り尽くした。これが/これも削ぎ落としだ。切り詰めて、そして、あとは観るだけで充分だ。
古川日出男(作家)