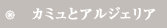アルベール・カミュは1913年11月7日、アルジェリア東部の港町ボーヌ(現アンナバ)に近いモンドヴィ村で生まれた。ワインの輸出業リコム社に勤めていた父親リュシアン=オーギュストがこの農場のぶどう園の管理を委ねられていたからである。
しかし、第一次大戦の勃発(1914年夏)とともにリュシアン=オーギュストは動員され、マルヌの戦いで砲弾を受けて入院、10月11日に死去した。遺体は入院先のサン・ブリユー(ブルターニュ地方)の墓地に埋葬された。映画は、この父親の墓地を息子が訪れるところから始まっている。父親はアルザス出身の移民一代目、とカミュは家族から聞かされ、そう信じきっていたが、近年の研究ではボルドー近辺出身の曾祖父が一代目、カミュの父は三代目ということがわかっている。
夫を失った母親(彼女もまたスペイン系移民の三代目)はそのショックで難聴になる。そして二人の息子、四歳のリュシアンと生後9カ月のアルベールとを連れてアルジェの貧民街にある彼女の母の家に居候となる。冷たく、厳しく、押し付けがましい祖母、愛情を言葉で示す事の出来ない寡黙な母親、そして勉強机も本もない貧窮の中での生活、その貧しい家での母と子との生活は、最初のエッセイ集『裏と表』(1937)との重要な主題となるであろう。
しかし、少年アルベールは少年時代決して不幸ではなかったようだ。なによりも<太陽>と<海>とがあった。「私の少年期を支配していた太陽は、私から一切の怨恨を抜き取った」と彼は後に書いている。そして木曜と日曜とにはボールを蹴ることに夢中になるサッカー少年だった。
先生にも恵まれた。いち早く少年の才能に目をとめた中学校のジェルマン先生、高校の哲学級で出会い、少年の病(結核)を心配し続けたジャン・グルニエ。カミュはこの『孤島』の作者を生涯敬愛し続け、グルニエもこれに答えた。カミュの死後にグルニエが書いた追悼文は次の美しい句で閉じられている。
「小さな火花のつぎに大きな炎が続く」
大学卒業後もカミュは定職につかず、家庭教師をしたり、巡業役者をしたり、弁士をしたり、新聞原稿を書いたりしながら貧乏生活を続けていた。その間に結婚もしている(一年後に離婚)。最初の定職は1937年から気象学研究所、その次が
38年にアルジェで創刊された左翼系の新聞アルジェ・レピュブリカン紙である。カミュが記者としてアルジェリア北東部のカビリー地方の悲惨な状況についてこの新聞にルポルタージュを書き、植民地体制をいち早く告発したことは忘れられてはならない。
39年9月第二次大戦の勃発とともに新聞の検閲が激しくなり、アルジェ・レピュブリカン紙の後を継いだソワール・レピュブリカン紙は廃刊に追い込まれる。失職したカミュは友人の紹介でパリ・ソワール紙に勤め口を見つけ40年3月本国に向う。40年6月フランスの敗北とともに各地を転々とし、一時期は二番目の妻の郷里であるオランに帰っているが、42年7月からは結核の療養をかねてまたフランスへ。しかし11月、英米軍がアルジェに上陸したため、アルジェリアはドイツ占領下のフランスと切り離され、カミュは故郷に帰れなくなる。しかし『異邦人』(1942)『シジフォスの神話』(1942)が評価され、彼はガリマール書店に職を得て43年の暮れからはパリに住み始める。
その後のレジスタンスにおける活動、コンバ紙による言論活動、『ペスト』の刊行(1947)によって、カミュは作家としての地位をかため、戦後フランスの知的世界に大きな影響を与えた。この時代、パリに居を構えながらもほとんど毎年のようにアルジェリアを訪れている。あるときは子供たちと一緒に妻の出身地であるオランに、あるときは骨折をした母の手術に立ち会うために、またあるときは彼の知らないサハラ砂漠を旅するために。一時期は、パリの社交的な生活が厭になったのだろう、アルジェリアに引きあげることを考え、友人に家探しを頼んだりしている。
1954年11月1日、アルジェリア全土で民族解放戦線(FLN)が一斉に蜂起した。フランス政府は戦争と認めなかったが、一般にはアルジェリア戦争と呼ばれるこの抗争は、1962年のアルジェリア独立まで続く事になる。
当初のカミュはオプティミストで、55年2月、アルジェを訪れたときの新聞インタヴューでは、自分のインスピレーションの源泉であるアルジェで一年のうち6ヶ月は過ごしたいとのんびりしたことをしゃべっている。彼の政治的立場も当初は明快であった。55年6月には、週刊誌で、アルジェリア<叛徒>のテロリズムを非難すると同時にフランス軍による武力弾圧を告発し、解決の道として、フランス人とイスラム教徒の真の代表を選ぶ公明な選挙を提唱している。彼の頭の中にアルジェリアの独立という文字はなく、二つの民族の両方に権利を保証するような連邦制の共同体というのが彼の構想であり、立場だった。900万人のアルジェリア人の民族解放が100万人のフランス系住民の追放を必要とするとは考えていなかったのである。
しかしこうしたオプティミズムは、1956年1月以後次第に打ち崩されていく。この月カミュは、フランス側のリベラル派とイスラム穏健派とで市民休戦委員会を作り、そのアピールを出す目的でアルジェを訪れたのだが、情勢はすでに緊迫化していた。極右植民地主義勢力は軍の一部を巻き込んで、自分たちの権益をまもるためにイスラム教徒に譲歩する気配はなく、カミュの講演会を自分等に対する挑戦と受け止め、当日、講演会の会場周辺の広場には千人をこえる極右のデモ隊が押し寄せた。他方、アルジェリア人も千人を越える数でいざというときに備え
広場の近辺に待機していた。映画にあるカミュの講演会はこうした雰囲気のなかで行われたのである。
デモ隊の中から発せられた「カミュを銃殺せよ」の声は彼にとって大きな衝撃であったろう。さらにその二週間後、内閣が変わり、アルジェ総督に強硬派のラコストが任命された。これによってカミュは、自分の構想が活かされる場がないことを悟ったのだろう、以後、アルジェで逮捕された友人の釈放運動には関与したが、アルジェリア問題について発言をすることは一切拒否するようになる。
カミュのこの沈黙はしばしば批判の対象になった。フランス軍による残虐行為、拷問が明るみに出たときに、多くの知識人が抗議の声をあげたが、カミュは発言をしなかった。しかし1957年ノーベル賞を受賞したときにはこの沈黙を破らざるを得なかった。ストックホルムでの多くの質問が此の点に集中したからである。しかし、双方の側の暴力と殺人を拒否するという、それまでに語ってきた以上のことを語りえたわけではない。学生たちの討論会の席上での一つの発言はよく知られている。
「私は正義を信ずる。しかし正義より前に私の母を守るであろう」。
彼は正義が解放戦線の側にあると考えていたのだろうか。にもかかわらずFLNの支持に踏み切れなかったのは、無差別テロの危険が母親に及びうるというこの一点だったのか。レジスタンスのときには暴力も殺人もカミュは受け入れたのに、という批判に対してカミュは答えるすべを知らなかった。
1958年5月、ドゴールが政権の座につく。ドゴール内閣の文化大臣となったアンドレ・マルローは、アルジェリアに常駐する<フランスの良心の大使>になってくれとカミュに求めたが、カミュはこれを固辞し、以後は芝居と『最初の人間』の執筆に専心することになる。  1960年1月4日、カミュは車で事故死する。現場近くの泥のなかに黒皮のカバンが落ちていて、中に『最初の人間』の草稿があったという。この草稿は長い間家族が出版を許可しなかったが、1994年にようやく出版され、今日日本語でも読むことができる。ちなみに<最初の人間>とはまず第一にアルジェリアの土地に初めて根をおろしたカミュ家の第一世代である(とカミュは信じていた)父親のことである。と同時に第二に、文化—教養の背景が何もないところに、ブルデューの言葉を借りれば<文化資本>のない貧しい環境に育った息子自身のことでもあるだろう。何もないゼロの地点から出発した人間、これが<最初の人間>ということになろうか。
1960年1月4日、カミュは車で事故死する。現場近くの泥のなかに黒皮のカバンが落ちていて、中に『最初の人間』の草稿があったという。この草稿は長い間家族が出版を許可しなかったが、1994年にようやく出版され、今日日本語でも読むことができる。ちなみに<最初の人間>とはまず第一にアルジェリアの土地に初めて根をおろしたカミュ家の第一世代である(とカミュは信じていた)父親のことである。と同時に第二に、文化—教養の背景が何もないところに、ブルデューの言葉を借りれば<文化資本>のない貧しい環境に育った息子自身のことでもあるだろう。何もないゼロの地点から出発した人間、これが<最初の人間>ということになろうか。
「『最初の人間』はアルジェリア生まれのフランス人とその子孫にとって、まさに現在、熱狂的に支持される小説である。」―R.Laffont辞典より
1960年にアルベール・カミュは、「最初の人間」の未完の原稿を残し、自動車事故のため46歳の若さで亡くなった。「最初の人間」は、「自分の最高傑作となるだろう」とカミュ自身が予言していた自伝的作品である。当時、アルジェリア独立戦争という時代的状況の中、遺されたカミュの妻と友人たちは出版に反対した。本に記されていたカミュの非暴力の主張が、当時の主流である思潮からかけ離れていたからだ。
そして、「最初の人間」は1994年まで出版されることはなかった。カミュの娘、カトリーヌ・カミュは父の成長期とその小説を書くプロセスの双方に独自の洞察を与えようと、未完の草稿であったが、そのまま未改稿で出版することを選んだ。
40歳の男、ジャック・コルムリが子供時代のアルジェリアに帰郷するという物語は、三人称で書かれている。この本は、自分探しの物語であるとともにフランスの偉大な小説家にして思想家の遺書でもあるのだ。自身の起源をたどって、コルムリは子供時代を思い出し、彼が決して知ることのなかった父(1歳の頃、第1次大戦で戦死)について空想する。
カミュは自身の二面性についてさらけ出す。「ペスト」「異邦人」の作家で、パリの知識人から祝されるノーベル賞受賞者である自分。父親がおらず、豊かでないながらも自ら道を切り開いた自分。これが小説として結実した。
コルムリの過去の探求と、自身の個人的な世界への旅は、読者に対して、読者自身のカミュに対する考え、すなわち実存主義や不条理観など、カミュに結び付けられる概念を、改めるよう促す。
また、作品の中では、彼の生まれ育った故郷、アルジェリアに対する深い愛着も伝わってくる。カミュにとって、フランスは、いつもある意味異国であったのだ。その他にも、カミュと母との関係、母への深い愛、アルジェリアの荒廃した地域での、母と叔父と共に過ごした貧しい暮らしを回想する。
「最初の人間」は多く主観的に、アルジェの暮らしを生き生きとした表現で、詩的な視点から描かれる。また、カミュのサッカーに対する情熱、働く者に対する深い尊敬は、特筆に値する。
この本は1994年4月に出版されると、版元のガリマールでさえ予想していなかったセンセーションを巻き起こした。最初の週に5万部、1か月で16万5千部の売り上げを記録。20社もの国際的な出版社が直ちに翻訳権獲得の列に並び、2005年までに35カ国で出版された。フランスではポケット版が2000年に出版され、
10万部を売っている。
「最初の人間」はメデイアの大きな興味の的となった。フランス全土はともかく、海外においてもまだ翻訳書が発売される前から大きな反響をよんでいた。自伝的な作品に対する一般的な流行があるとはいえ、カミュの最後の原稿で、その死後の出版されたことは、大事件と言っても過言ではなく、いかに彼の作品がいまだ世界の共感を呼んでいるかを強調するものだ。
言うまでもなく、「異邦人」は出版から60年以上たった今日もフランスではベストセラー小説のひとつである。
特有の官能性と明晰さに満ちたカミュの声は明らかだ。実際、カミュを読み始めるなら、「最初の人間」から読むべきだという人もいる。
※「最初の人間」は、フランスで59万2千部を売上、35カ国、32言語に翻訳、出版されている。
「最初の人間」を読み、映画化を考えた時に、私はすぐにジャンニ・アメリオが思い浮かびました。10年の間に、彼の監督する『小さな旅人』(92)、『LAMERICA』(94)、『家の鍵』(04)の3本の映画をともに製作していて、彼を人間としても監督としてもよく知っていました。
具体的に、なぜ彼を起用したのには3つの重要な理由があります。
- 一.
- 子供の演出にかけては、フランス語を話す監督として、最も才能のある監督の一人であると確信しているから。『小さな旅人』『家の鍵』の際には、彼は若い主演者に、演技の真の正確さ、抑制された大人の役者に匹敵する感情を与えました。
- 二.
- 彼がアルベール・カミュに似た家族史を持っていること。父の不在(カミュの父親は戦死、アメリオの父は彼の家族をカラブリアに残したままアルゼンチンに移住)、母とそしてやや強権的な祖母という、女性によって営まれた貧しい家庭に子供時代を送り、天佑のごとく、教師が彼の天職の道を歩むように家族を説得してくれたことなども共通しています。
- 三.
- 両者ともに南からきた男であること。カミュはモンドヴィ生まれ、アルジェリア育ち。アメリオはカラブリア州の中心、サン・ピエトロ・マジサーノ村の出身です。
私はフランスとアルジェリアの共有するストーリー、とりわけフランスとアルジェリアの集合的な体験は、イタリア人にはよく知られていないという事実について、懸念がありました。しかし、それから、私はフランスーアルジェリア映画史上の2本の象徴的な映画が、どちらもイタリア人によって撮られたことを思い出しました。『アルジェの戦い』はジッロ・ポンテコルヴォが、そして『異邦人』、カミュの小説の最初の映画化に携わったのは、ルキーノ・ヴィスコンティでした。 
一方、私は『最初の人間』の映画化権を取得するために娘のカトリーヌ・カミュを説得しなければなりませんでした。出版社のガリマール社は、彼女がジャンニ・アメリオの映画を試写できるよう取り計らってくれ、そしてもし、全てがうまくいったら、会議を開くということになりました。彼の映画を見たことが決め手となり、カトリーヌ・カミュはすぐにジャンニ・アメリオ監督を信頼し、自身の家族の記録を開示すると言ってくれました。彼女はもちろん、脚本のチェックはしましたが、大半はアルベール・カミュの作品に対して誠実であるように、という要求のみでした。
彼女は映画を気にいって、小説からの色々な情景と、一家の記録からインスパイアされたものと、またジャンニ・アメリオの個人的な想い出が、実にうまく構成されていると感心してくれました。